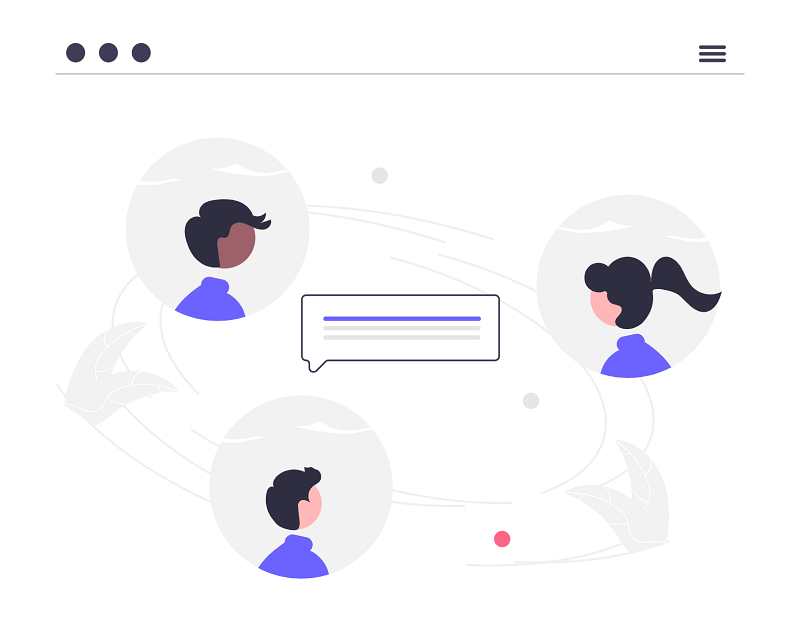
春の入門祭り2025 8日目です。
はじめに
はじめまして。製造・エネルギー事業部に所属しております、金森と申します。私は自動車メーカーからフューチャーへと異業種転職してきたという、少し珍しい経歴を持っております。
春の入門祭りということですが、春は新しいスタートの季節です。学校や職場など、多くの人が変化の中で新たなチャレンジに向き合う時期ではないでしょうか。
今回は、そんな季節にぴったりのテーマである 「チーム異動などで環境が変わった後の立ち上がり方」 についてお話ししたいと思います。
転職という大きな環境の変化も経験しているからこそお伝えできる、心構えやちょっとした工夫をご紹介していきます。
環境変化では「ゼロから」ではなく「編集から」始める
新しいチーム、新しいプロジェクト、新しいドメイン——IT業界では異動が日常的に発生します。異動先の業務は未知の連続に見えるかもしれませんが、私は「ゼロからスタート」だとは考えないようにしています。むしろ、「編集から始める」という意識が大切だと思っています。これはどういうことかというと、「チームにある暗黙知」や「既存のプロセス」「使われている用語やツール」など、既に存在しているものにまず自分を馴染ませ、少しずつ意味づけや関わり方を変えていくという考え方です。
最初から変革者のようなスタンスで入ると、摩擦が生まれやすく、信頼を得るのも難しくなります。一方で、まずは今あるやり方を尊重し、「なぜそのように運用されているのか?」を観察・理解した上で、 「もしこうだったらもっとよくなるかもしれない」といった編集者的視点を持つことで、変化の受け入れと提案のバランスの取れた動き方ができるようになります。
「観察」と「共感」は、最初のタスクである
異動後の最初の1〜2週間で意識しているのは、「観察」と「共感」のインストールです。
特に観察では、「誰がキーマンなのか」「どのような暗黙のルールがあるのか」「過去にどんな課題があったのか」といった点を丁寧に掴むようにしています。Slackの過去ログを読み漁ったり、タスク管理ツールの履歴を遡ったりして、表面的な情報だけでなく、空気感や歴史的な背景にまで目を向けることを大切にしています。
一方で、共感はもっと感情に関わる部分です。
初対面のメンバーが抱きやすい「この人は味方だろうか? それとも違うのか?」という無意識の問いに対し、自然と「味方ですよ」と伝わるような態度を取ることが重要です。
そのためには、ちょっとしたリアクションやSlackでの軽いツッコミ、さりげない称賛が意外にも効果的です。
技術があるだけでは、タスクは進めどチームに馴染むことはできません。「この人と一緒に働いていて楽しい」と感じてもらうことが、結果的に生産性の向上、よりよい製品にもつながると実感しています。
自信がないまま始まってもいい
新しいプロジェクトに入るとき、特に異動直後や転職後は、「自分に何ができるのか?」「本当にこのチームの役に立てるのか?」という不安がつきまといます。
私自身、IT業界に飛び込んだ当初は、シェルの使い方も知らず、「フロントエンド」「バックエンド」といった言葉の意味すら曖昧な状態でした。そんな中での最初のタスクは、自分の開発環境を構築すること。しかし、当たり前のように飛び交う専門用語に戸惑い、手順書の内容すら理解が追いつかず、環境構築だけで2週間もかかってしまいました。
Slackではどんどんやり取りが進み、チームは次のフェーズへ向かっている。一方で自分は「まだスタートラインにも立てていないのではないか」と焦りと劣等感を感じていました。
しかしあるとき、「とにかく手を動かしながら覚える」「全部を理解しようとせず、わかるところから地道に拾う」というスタンスに切り替えました。すると、知識は後からついてくること、そして何よりも「今わからないことを素直に聞けること自体が、チームの前進に役立つこともある」と気がつきました。
例えば、複雑化した要件定義を読み解くとき、「これはそもそもなぜこういう仕様なのでしょうか?」と素直に聞くことで、実は誰も気づいていなかった抜け漏れが見つかったこともありました。スキルが足りないことを補うには、恐れずに聞く勇気が非常に有効だと実感しました(※もちろん自学での成長も重要ですが)
最初から自信を持つ必要はありません。むしろ自信がないからこそ謙虚に学び続けられるし、気づける視点があります。それこそが、新しい環境に飛び込んだ人の大きな武器になると、今では思っています。
最後に
「技術ブログ」と聞くとコードや実装の話に偏りがちですが、人や組織の変化が絶えないITの世界だからこそ、「どう立ち上がるか」「どう馴染むか」という視点も、立派な技術知見だと私は考えています。
これはあくまで私の個人的見解になりますが、誰かの助けの一助にでもなればと思います。
次は実際に「技術的なブログ」を書けるように精進します。ではまた。