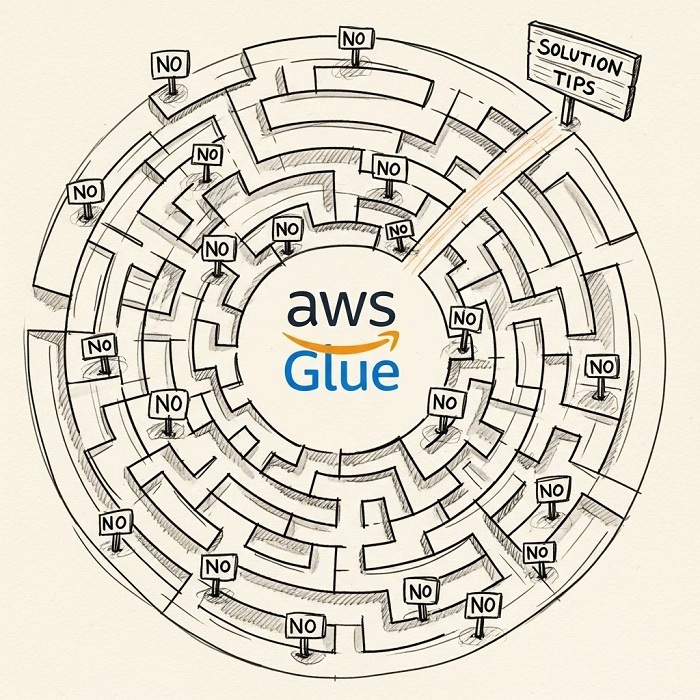
はじめに
TIGの八木雅斗です。
業務でGlue Python Shell Job(以降、Python Shell)を利用する機会があったのですが、「Lambdaとかだと簡単にできるのに、Python Shellだとできないんか~」とか、ドキュメント上でPySparkジョブ or Python Shellのどちらについて記載しているのか分かりにくかったりと、戸惑うことがありました。それらの悩みポイントをまとめます。
ログ出力先のCloudWatch Logsのロググループを選択できない
PySparkジョブでは、--continuous-log-logGroupでロギング先のロググループを選択可能です。
一方、Python Shellでは出力先のロググループを指定することはできません。
ログは下記のロググループに出力されるよう設定されており、AWSアカウント上のすべてのPython Shellのログが、以下のロググループに出力されるようになっています。
- 標準出力先
/aws-glue/python-jobs/output
- 標準エラー出力先
/aws-glue/python-jobs/error
そのため、指定したロググループにログを出力したい場合は、Pythonスクリプト上からCloudWatch Logsにログを送信する必要があります。
具体的な対処法としては、boto3を利用した下記のようなカスタムハンドラをルートロガーに設定し、指定したロググループ/ログストリームにロギングする等があります。
class CloudWatchLogsHandler(logging.Handler): |
※Pythonスクリプト上で出力するアプリケーションログでなく、Python Shellが出力するシステムログに関しては引き続き/aws-glue/python-jobs/xxxに出力されます。
自動でメトリクスが取れない
下記の設定もPySpark用の設定であるため、有効化してもメトリクスは取得できません。
--enable-job-insights--enable-observability-metrics
Google検索すると、Monitoring with AWS Glue job run insightsがヒットして設定できそうに見えますが、よく見ると「Spark and PySpark jobs」配下にあり、PySpark用の設定値であることが分かります(見落としがち)
もしCPUやメモリの利用状況をモニタリングしたい場合は、下記のようにpsutilなどを使ってモニタリングする必要があります。
import time |
選択できるPythonのパッチバージョンが古い
2025.08現在、Python Shell ジョブでは、Pythonのバージョンにv3.6またはv3.9を利用できます。
ただ、Python Shellでのv3.9のバージョンは3.9.x系の最新版かと思いきや、2022年1月にリリースされた3.9.10になっています。
# Python Shellにて |
開発環境やビルド環境においてバージョン違いで動かなくなることを避けるため、3.9.10まで指定する必要がありました。
デフォルトで利用できるライブラリのバージョンが古い
Python Shellの実行環境では、boto3などのライブラリがサポートされており、追加の設定なしに利用できます。
ただし、いずれのライブラリも微妙に古いため、ものによっては使えない機能がある可能性があります。
# Python Shellにて |
もし他のバージョンのライブラリを利用したい場合は、PyPIに登録されているモジュールを追加できる--additional-python-modulesオプションを利用することで差し替えることが可能です。
–additional-python-modules オプションでコンマ区切りの Python モジュールのリストを指定することで、新しいモジュールを追加したり、既存のモジュールのバージョンを変更したりできます。
存在しない実行パラメータにアクセスするとSystemExitエラーで落ちる
Python ShellではgetResolvedOptionsを利用して実行パラメータにアクセスできます。
しかし、存在しないパラメータにアクセスしようとすると、Exceptionを継承していないSystemExitのエラーが発生するようになっているため、Exceptionでcatchができません。
具体的には、argparse.ArgumentParserクラスを継承したインスタンスの以下のparse_known_argsメソッド内でArgumentErrorが発生し、sys.exit(2)が呼ばれるようになっています。
- https://github.com/awslabs/aws-glue-libs/blob/9d8293962e6ffc607e5dc328e246f40b24010fa8/awsglue/utils.py#L119
- https://github.com/python/cpython/blob/06fc882eac0e59220a7b8b127a1e7babe0055d45/Lib/argparse.py#L1859
もしオプションの実行パラメータを設定する場合は、PEP 8で非推奨な方法になりますが、例外の基底クラスであるBaseExceptionでcatchする必要があります(↓例)
import sys |
マネジメントコンソール上での変更で想定外の差分が発生する
原因は不明ですが、マネジメントコンソール上から設定変更を行うと、下記の実行パラメータがPython Shellのデフォルト値に勝手に変更されてしまうことがあります。
- glue_version
- デフォルト値:
3.0
- デフォルト値:
- –enable-job-insights
- デフォルト値:
false
- デフォルト値:
- –enable-observability-metrics
- デフォルト値:
false
- デフォルト値:
- execution_class
- デフォルト値:
STANDARD
- デフォルト値:
💡利用ツールのバージョン Terraform v1.12.2 / AWS provider v6.3.0
いずれのパラメータもPython Shellの挙動に影響しないですが、Terraformで管理しているとplan実行時に差分が表示されノイズになるので、下記のようにデフォルト値を設定しておくと良いと思います。
resource "aws_glue_job" "sample" { |
※ちなみに、Glue Python Shell Jobという名前ですが、GlueVersionの設定は動作に影響しないようです。実際に、AWS CLI経由でGlueVersionを1や2に設定しても、Python v3.9の環境で正常に起動していました。
GlueVersion 設定は Python シェルジョブの動作に影響しないため、GlueVersion をインクリメントするメリットはありません。
AWS Glue バージョンサポートポリシー
最後に
Python Shellをはじめて使う時に戸惑いそうな仕様について共有しました。
今回の記事では、ややPython Shellのネガティブな内容が多くなりましたが、実行時間制限がLambdaの15分よりもはるかに長い48時間であり、サーバーレス環境で実行できる等のメリットがあるため、Lambdaでは処理できないケースでは選択肢になると思います。
性能限界が1DPU(4vCPUと16GBのメモリ)ということも頭に入れつつ、もし非機能要件を満たせない可能性がある場合はECSに移行しやすい構成にしておくと安心して利用できると思います。
Python Shellは細かなつまづきポイントが多いので、これから使おうと思っている方のお役に立てれば幸いです🙏